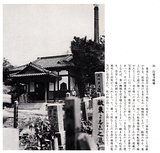*画像をクリックすると拡大画像が別ウィンドウで開きます。
奈良市斎苑旅立ちの杜の完成により廃止になった東山霊苑火葬場です。この地に1916年(大正5年)3月3日に開設されました。
この建物は、1968年(昭和43年)2月21日に起工式、12月10日に完成しました。
何度か改修をして、1982年(昭和57年)9月16日には新しい炉に更新を行い高煙突も無くなり現在の姿になりました。
建物上の茶色いルーバーは、新しい炉の排気筒を隠す為のもので、建設当初はありませんでした。
ここに来るのは、父親の火葬の時以来になります。
歴史のある火葬場でも、廃止の日はひっそり終わります。
多くの方の最後を見送った火葬場の最後を見届ける人は誰も居ない事が殆どです。
この写真は、廃止日の2022年3月31日の18時頃に撮影したものです。
雨が降り肌寒い日でした。
市役所からは誰も来ないだろうと思ったら、
仲川げん奈良市長と、鍵田美智子市議が来られました。
鍵田さんは、この当時は火葬場を管轄する市民環境委員をなされていました。
この建物の竣工式は、鍵田忠三郎市長が立ち会われていましたので、現在の市長と、完成当時の市長の縁の方が立ち会われた事になります。
なんか、感慨深いです。
この火葬場は、奈良市の職員が直接火葬業務を行っていました。
長年業務に携わってきた方もいらっしゃいます。
市のトップが最後の日に来られて労いのお言葉を述べられていましたが、大変良い事だと思います。
市民からは全く注目もされない古い火葬場、それも17時も過ぎた時間に市長が足を運ばれるとはビックリしました。
いつもは関係者を写真に撮る事も掲載する事はないですが、公人だからいいですかね。
現場と市役所の職員と15人くらい居たのかな。
せっかくなので、市職員のカメラで全員の記念写真を撮ったらいかがですかと提案しなかった事が心残りです。
寒い日だけど温かい最後の日でした。
東山霊苑火葬場というだけあって、霊園内にあります。
旅立ちの杜へと続く道から入ります。
山沿いあるから遠くの方まで見えますね。 よく見ると郡山のイオンが写っていました。
すぐ近く、手前のコンクリートの建物は、高円芸術高校(高円高校)です。
高円高校の第一期卒業生の方とお話する機会があって、授業中に火葬してる臭いがする事もあったと聞きました。
でも高円高校が開校したのは1983年で、炉の更新後です。
後で触れますが、当時の炉としては強力な再燃焼炉を備えてるからか点火直後でも煙は出ません。
たぶん、田畑の野焼きの臭いだったのではないかと思います。
なんか、城壁みたいですね。
城壁みたいな所は回廊のようになっていて、待合室やトイレ、管理室などがあります。
蔦の合間の格子は待合室の窓です。
コンクリートやタイルは古くなっていますが、完成当時は洒落たものだったでしょう。
ここと同じ小学校の校区に住んでいますので、子供の頃は近くの友達と時々ここで遊んでいました。
懐かしい
火葬場正面です。
駐車場は霊柩車やマイクロバスが一時的に停められる程度の広さです。
乗用車などは霊園入口にある駐車場に停める事になります。
火葬中は、火葬場内で待ってる方は非常に少ないので、一時的な駐車になります。
火葬場本体よりも目立つ構造物があります。
残骨灰を納めている供養塔です。
3枚目の写真の真ん中の八角形の建物は、簡単な葬儀も行える式場になりますが、使用頻度はかなり低かったです。
その裏に待合室やトイレがあります。
式場の前にバケツなどが写っています。
火葬場は墓参の方の水場やトイレでもあります。
建設当時は、残骨灰を丁重に保存するという概念は、あまり無かったと思います。
当時としては、かなり珍しい存在だったのではないかと思います。
設計の指導は、元奈良国立博物館館長の石田茂作氏が行われたようです。
設計上は、210立方メートルの残骨灰が納める事が出来ます。
かなりの容量ですね。
説明文には、火葬の残った焼骨を収蔵しと書いていますが、墓地埋葬法の焼骨ではなくて残骨灰が納められています。
分かり易いように焼骨という用語を使ったんだと思います。
供養塔については話が尽きません。
また後で触れたいと思います。
1枚目の画像は、改築前の火葬場で、2枚目は古い航空写真と現在の航空写真です。
改築前の火葬場は、供養塔の辺りにあったようです。
旧火葬場の写真を見ていると、煙突が奥の方にあるなと思っていました。
古い航空写真を見ると、煙突のある火葬棟から左下にもう一棟建物が繋がっているようにも見えます。
古い火葬場では時々ある配置です。
旧火葬場の画像に写っている火灯窓のある建物は、もしかしたら告別棟なのかも知れません。
供養塔は、火葬場本体の完成から一年ほど遅れて完成しています。
火葬場の完成後に旧火葬場を撤去して、そこに供養塔を建てたのだと思います。
それで供養塔の完成が遅れたのでしょう。
大正5年以前にも、ここに火葬場があったという話も聞いた事があります。
地元管理の野焼きに近い簡易火葬場だったのでしょう。
一つ気になるのは、1909年(明治42年)に近くに陸軍病院が出来た事です。
現在の奈良教育大学の南東にあった国家公務員住宅の場所です。
昔の大きな病院は、霊柩自動車が無い事と、感染症で亡くなった方を火葬する為に敷地内や近くに火葬場がある事も多かったようです。
現在でも、国立療養所大島青松園のように現役の火葬場がある所もあります。
全くの想像ですが、簡易火葬場だと不便で火葬能力的も劣り不都合も生じたりして、市営化して近代的な火葬場に整備したのかも知れません。
それだけが火葬場建設の理由ではないとは思うけど、火葬場建設の一つの切欠だった可能性はあるような気がします。
後日に続く